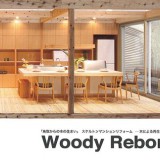聞き書き
『建築とニワトリ』の記事で、「今のうちにもっと長老たちから、昔話や行事とかをきちんと聞いて記録しておきたいね。」と記載していたとおり、先日、私たちが暮らす集落の長老から、昔の暮らしや文化についてお話を聞く機会を設けていただきました。
私たちが暮らす集落

智頭町内の重要文化的景観に指定された集落と同様に、私たちの集落でも山仕事で生計を立てていた家が多かったそうです。
当時の暮らしや仕事内容、行事、慣習、娯楽など話は尽きませんでした。特に植林が進む前は、山菜やきのこが豊富に採れたという話が印象的でした。
蔵に保管されていた「大和こたつ」※1

昔の暮らしを知る中で、暮らしや営みが周囲の自然環境と深く結びついていたこと、また家族や集落で人々が苦楽を共にし、不便な暮らしの中でも心豊かに過ごしていたことを改めて感じました。
「私たちが今できることは何か…?」
地域で同じ価値観を持つ人たちがつながり、地域の課題や可能性について共に楽しみながら考えていくことの大切さを、最近あらためて実感しています。地域が抱える課題は、当たり前のことですが私たちの暮らしそのものに直結しています。そうした課題を、その土地ならではの視点や感覚で思考することが、地域の風景を育む取り組みにつながっていくのだと考えています。
田舎には、世界的な環境問題や社会課題の解決につながるヒントが眠っているような気がしています。日々の暮らしの中にある「当たり前の豊かさ」に改めて気づくこと、それが私たちにできる第一歩なのではないでしょうか?
設計事務所として、地域の文化や自然、人々の暮らしに根ざした視点で風景と調和する仕事をしていく。この地で受け継がれてきた美しい風景を守り、次世代に継承していくことも、私たちの大切な仕事の一つであるという思いを強くする日々です。
地域のお年寄りのお話の中にも、「私たちが今できることは何か…?」その答えのヒントがたくさんあることに気付かせてもらいました。
今日、事務所周辺で採れた柿と栗

※1「大和こたつ」薪風呂の残り炭などを箱の中の「火入れ」に入れる。寝るとき布団の足元に入れ、家族が四方から布団を敷いて暖をとっていたとのこと